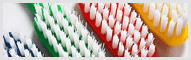|
◆ カバさん新聞 ◆ 第1回 ドクターコラム (2007-09-14) 理事長 岸田 泰栄 江戸深川の事について少し書き示してみたい。 江戸時代は火事が多く、そこで暮らしていた町民は色々な策を講じて火事から身を守った。堀を作ったり、火消し組もそうである。 出火すると町民はもとより武家人も協力して火消しをした様である。 いち早く火元を見つける事が一番大事で、その為随所(※ずいしょ)に火の見やぐらが立っていた。特に深川門前仲町の高さは六丈(約18メートル)の堂々とした火の見やぐらだったそうである。 火が近いと「カン・カン・カン」と連打し、遠いと「カン・カン」と二回打ち、 鎮火した時と見間違えた時は一回打って知らせるしくみになっていた。この時代は見間違えも多かったが、公儀は咎(とが)めて半鐘を打たなくなり火消しが遅れないよう咎(とが)めはしなかったそうである。大名屋敷の中で生活する家臣は長屋から屋敷をおとずれる者を塀の上から常に見張っていた。ひとたび火が出ると火消しの役目を負わされ、江戸の町を火から守った。 屋敷内のやぐらで半鐘を鳴らす事もあったそうである。 ・・・つづく ※随所…いたるところに・ほうぼうに カバさん新聞一覧へ |
Copyright 2007 © 医療法人 岸田会 All rights reserved. | プライバシーポリシー